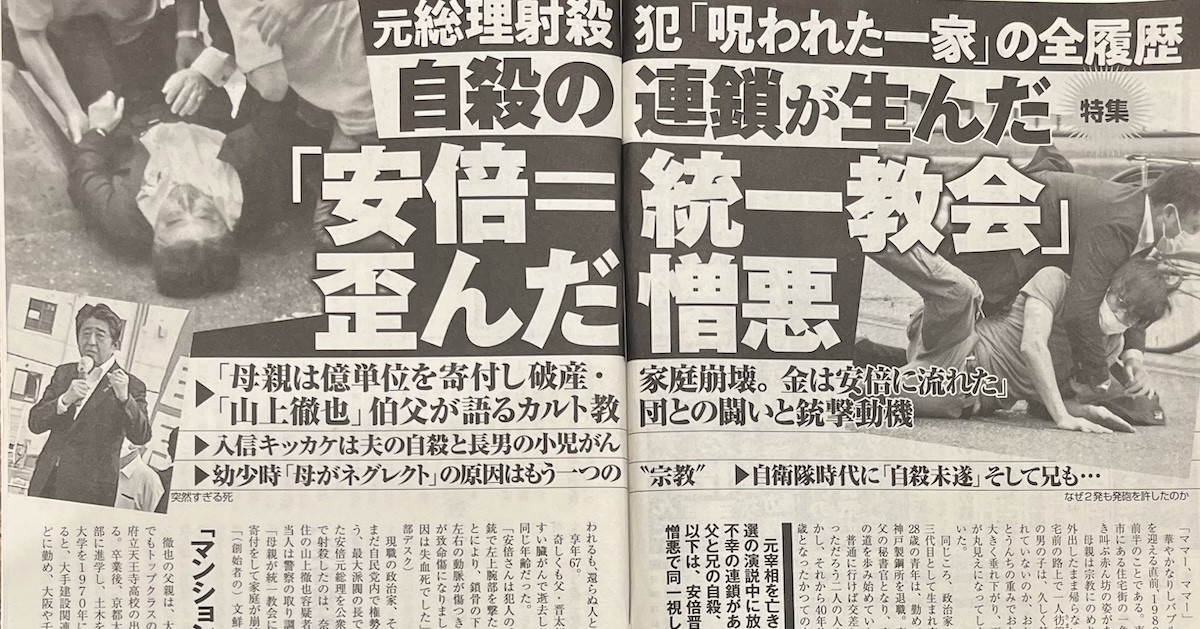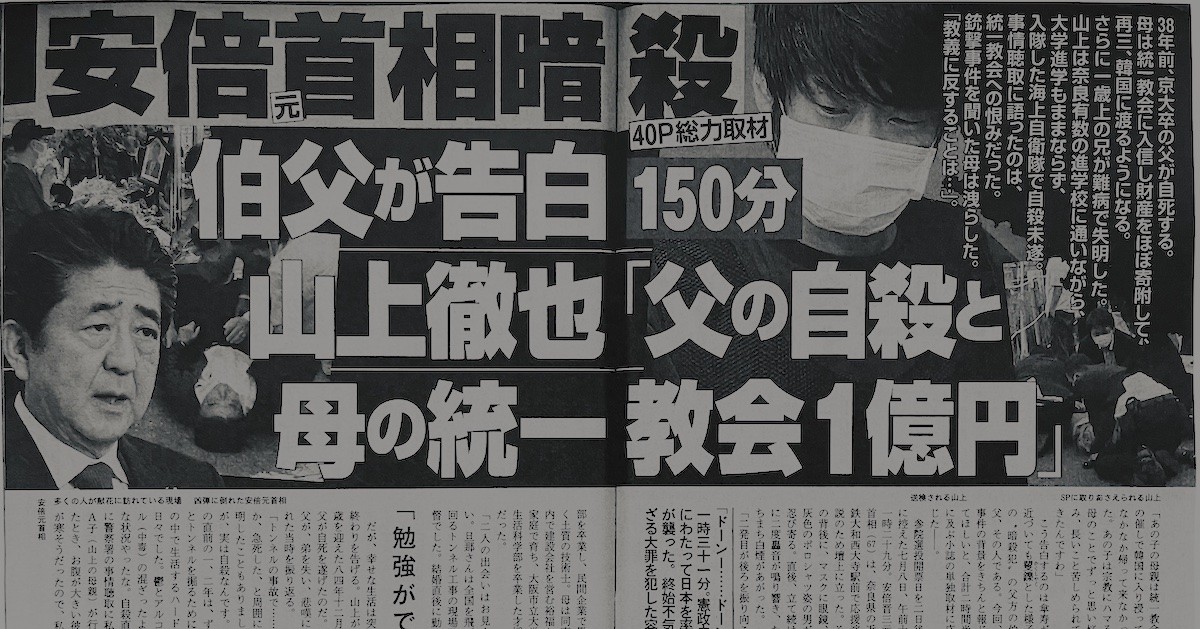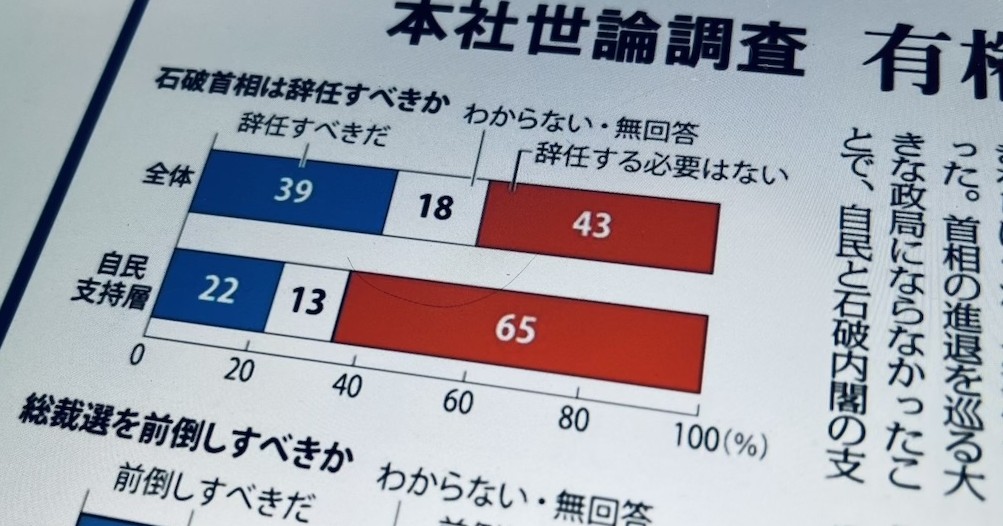迷走するコロナ“5類化”論議 真の論点は何か
新型コロナウイルス感染症の感染症法に基づく分類をいわゆる「2類相当」から「5類」に変更すべきか、いわゆる「5類化」問題をめぐって、議論が迷走しています。
今回は、新型コロナウイルス感染症の「5 類化」問題について、複雑な法制度をからめながら整理し、真の論点を考えてみたいと思います。
『楊井人文のニュースの読み方』は、今話題の複雑な問題を「ファクト」に基づいて「法律」の観点を入れながら整理して「現段階で言えること」を、長年ファクトチェック活動の普及に取り組んできた弁護士の楊井がお届けしております。
大手メディアが報じる内容やインフルエンサーの発言をうのみにせず、事実や法律に基づいた重要な論点を知っておきたい方に向けて、だいたい週1本以上のペースで執筆することを目指します。
のちのち有料版も考えておりますが、今は無料の配信を行っておりますのでぜひご登録ください。
(正確には「新型コロナウイルス感染症」ですが、以下「新型コロナ」と略称します。)
オミクロン株が主流になってから約1年。最近になって厚生労働大臣が新型コロナの類型見直しを進める方針を示し、関連するメディアの報道も増えてきました。
そうした中、新型コロナは「インフルエンザと同等ではない」「運用上すでに5類とほぼ同じになっている」「5類に変えても現場に影響はなく、問題は解決しない」といった見解が、主に医療関係者から発せられています。「5類ではなく、新しい類型に」という意見も出てきました(例えば、東京都医師会長)。

脇田隆字・国立感染症研究所所長の見解を伝えるテレビ朝日ニュース(12月15日)より
この「5類化」問題は、法律上の位置付けの問題である、ということをおさえておく必要があります。したがって、どのような法規制を行うべきか、行うべきでないのか、という視点を抜きにしてはこの問題は語れません。これまでのコロナ禍では、医療や感染症の専門家が語ることが圧倒的に多く、法律専門家の見解が皆無に近い状態でした。今回も、法律上の論点が理解されないまま、議論が行われているように感じます。
感染症に関する法律のしくみは複雑で、理解は容易ではありません。すべて理解するのは大変なので、重要なポイントさえおけばよいと考えています。
今回の記事は、次のような構成で、この問題を解説します。最後の結論部分から読んでいただいても構いません。真に議論されるべき論点は何なのかが見えてくるはずです。
〈前提①〉新型コロナは法律上「新型インフルエンザ等感染症」に分類されている
〈前提②〉位置づけの変更は法改正不要(例外あり)
〈ポイント①〉指定された病院だけで対応する体制を続けるのか
〈ポイント②〉無症状者や濃厚接触者の隔離を続けるのか
〈ポイント③〉水際政策を続けるのか
〈ポイント④〉緊急事態宣言等の行動制限を認めるのか
〈結論〉
〈前提①〉新型コロナは法律上「新型インフルエンザ等感染症」に分類されている
まず、現在の法律のしくみと新型コロナの位置付けについて、基本的な前提を確認しておきましょう。
感染症法は、約110種類の感染症を、その特徴や危険度などに応じて「1類」「2類」…などいくつかの大きなグループに分類し、患者を診た医師に届出を求めています。行政が感染症の発生や流行を把握し、それぞれの感染症に応じた対策を行うためです。
「1類」が最も危険性の高い感染症で、エボラ出血熱など7種類。「5類」が最も危険性の低い感染症で、季節性インフルエンザはじめ約50種類が分類されています(詳細な分類表はこちら)。
現在、新型コロナは感染症法上「新型インフルエンザ等感染症」というカテゴリーに分類されています(*1)。2009年ごろに流行した新型インフルエンザ(A/H1N1)と同じカテゴリーです。よく「2類相当」と言われますが「2類」に分類されているわけではありません。
次に、他の関連する法律との関係をみていきます。
【図1】

筆者作成
「新型インフルエンザ等感染症」に分類されている感染症(新型コロナ)は、②検疫法、③特措法のいずれも適用されることになっています(*2)。
わかりやすくいえば、②検疫法は「水際対策」(国外から感染症の流入を防ぐ措置)を行うための法律。③特措法は「行動制限」(患者かどうかに関係なく国民一般の行動を制限する措置)を行うための法律です。
つまり、「新型インフルエンザ等感染症」に分類されている限り、(検疫法による)水際対策や(特措法による)行動制限といった措置が想定されている(=そうした措置を行う権限を行政に与えている)、ということになります。
(*1) 感染症法6条7項3号。
(*2) 検疫法2条2号、特措法2条1号。
「2類相当」という表現は不正確
「2類相当」という言葉をよく耳にします。しかし、上の【図1】をご覧のとおり「新型インフルエンザ等感染症」(=新型コロナ)は、「2類」には適用されない特措法の適用対象となっており、「2類」と同等の扱いとは必ずしも言えません。感染症法上も「新型インフルエンザ等感染症」は、「1類」にできて「2類」ではできない対策を適用できる規定もあります(一時的な交通の制限など)(*3)。
では、これまでなぜ「2類相当」という表現が繰り返し使われてきたのでしょうか。
実は、新型コロナは当初「指定感染症」というカテゴリーに分類されていました(*4)。当時、厚生労働大臣が既存グループのどれに近いかを説明する際に「2類相当」と答弁していました(*5)。
その後、2度の政令改正で規制が強化されて「1類」の措置も可能になり、1年後に「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられて規制はさらに強化されました。実際、「1類」の措置も適用可能という大臣答弁がなされたこともあったのですが(*6)、その後も「2類相当」という表現が慣例的に使われてきたのです。
ですから「2類相当」という言い方は、法律上のものでも厳密な評価でもなく、慣例的な言い回しにすぎないということを確認しておく必要があります。
一方、今年9月26日から届出や入院措置の対象が変更され、現場の運用は、事実上「5類」に近づいたとか「5類相当」といった言われ方もしています。
しかし、措置の内容を比べると、下の【図2】のように季節性インフルエンザとの違いもかなり残っています。「5類相当」というのもかなり大雑把な表現でしかありません。
【図2】
(*3) 感染症法44条の4
(*4) 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令
(*5) 加藤勝信厚労相の国会答弁(2020年2月4日)など
(*6) 西村康稔コロナ担当相の国会答弁(2021年3月3日)
〈前提②〉位置づけの変更は法改正不要(例外あり)
新型コロナは「新型インフルエンザ等感染症」というカテゴリーに分類されていることを確認しました。ただ、かつて流行した新型インフルエンザそのものは「5類」の季節性インフルエンザと同じ扱いになっています。

新型インフルエンザを「新型インフルエンザ等感染症」から外すと厚労相が公表した当時の報道(東京新聞2011年4月1日付け夕刊)
2011年3月、厚生労働大臣が新型インフルエンザを「新型インフルエンザ等感染症」から外して、季節性インフルエンザと同じ扱いにすると公表しました。公表だけでこのカテゴリーから外すことができる制度になっています。(*7)(詳しくは以前の記事も参照)
新型コロナも厚生労働大臣が「新型インフルエンザ等感染症」から外すと公表するだけで、このカテゴリーから外れることになりますが、新型コロナは「インフルエンザ」ではないため、自動的に「5類」に移行するわけではありません。新型コロナの場合、論理的に次の4つの選択肢があります。
【図3】

筆者作成
①「5類」に位置づけるには、厚生労働大臣の決定(省令)だけで可能です(*8)。医師の届出は必要ですが、対策はかなり緩やかになります。法律上、以下の感染症と「同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるもの」であれば「5類」に指定できます。

②「指定感染症」に位置づける選択肢もあります。「1類」〜「3類」で用意されている対策メニューを取捨選択できるので、「1類相当」にすることも「3類相当」にすることも可能です。これも法改正は不要で、内閣の閣議決定(政令)だけでできます(*9)。新型コロナは最初の1年間この「指定感染症」でした。ただし、この扱いが可能なのは最長2年までです(*10)。
なお、「4類」も政令で指定できるのですが、動物や飲食物等を介して感染が広がるタイプの感染症を想定しているため、新型コロナの場合は当てはまらないと考えられます。
③感染症法上どのカテゴリーにも位置づけず、医師の届出が不要な感染症、従来からある風邪のコロナウイルスと同じ扱いにする選択肢もあります。この場合は、厚生労働大臣が「新型インフルエンザ等感染症」のカテゴリーから外す旨公表するだけで実現します。
④新しいカテゴリーを作るという選択肢もあります。感染症法上の既存のカテゴリーにあてはまらず、かといって風邪と同じように医師の届出や行政の対策を全くなしにもできない、という場合です。その場合は法改正が必要となり、一定の時間がかかります。
(*7) 感染症法44条の2第3項
(*8) 感染症法6条6項9号
(*9) 感染症法6条8項
(*10) 感染症法44条の9
以上の前提を踏まえ、新型コロナの位置づけを考える際に重要なポイントを4つを明らかにしていきたいと思います。
〈ポイント①〉指定された病院だけで対応する体制を続けるのか
〈ポイント②〉無症状者や濃厚接触者の隔離を続けるのか
〈ポイント③〉水際政策を続けるのか
〈ポイント④〉緊急事態宣言等の行動制限を認めるのか
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績